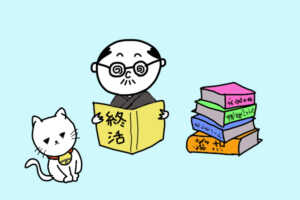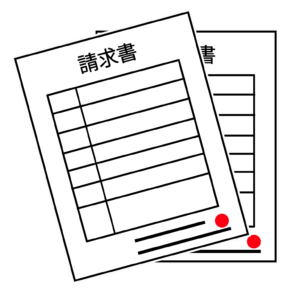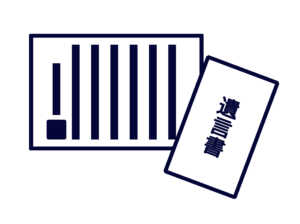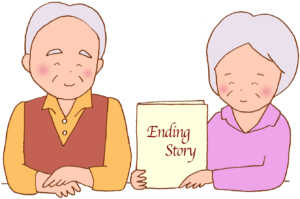「遺言(公正証書、自筆証書)の調査方法」
その他
父(母)は、生前、何か文書でしたため、「これで相続は心配ないからね」と言っていました。
おそらく遺言書があるのかと思うのですが、調べ方が分かりません。
このようなご質問は、多くのお客様から寄せられる質問です。
このコラムでは、公正証書遺言、自筆証書遺言がどこにあるのかを調査する方法についてご説明します。
目次
1 遺言とは
遺言書は、大きく分けて、公正証書遺言と自筆証書遺言がございます。
詳細な説明は別のコラムで取り上げましたので、こちらをご参照ください。
https://souzoku-katsushika.com/consultation-will/consultation-will-1/
2 公正証書遺言がどこにあるか調べる方法
平成元年以降に作成された公正証書遺言は、全国の公証役場という場所で公正証書検索システムによって調べることができます。
費用は無料です。
作成した場所でなくても(最寄りの公証役場で)検索することが可能です。
例えば、千葉の松戸公証役場で公正証書遺言を作成していたとしても、東京の葛飾公証役場でも、松戸公証役場で作成した公正証書遺言を調べることができるのです。
もっとも、だれでも自由に調べられるかというとそうではなく、相続人等の一定の利害関係を有する者である必要があります。
利害関係人は、以下の書類を揃えて申し出をすることで検索ができます。
- ①遺言者が死亡した事実を証明する書類(除籍謄本等)
- ②遺言者の相続人であることを証明する戸籍謄本
- ③申出人の本人確認の書類(マイナンバーカード、運転免許証等の顔写真付き公的身分証明書または実印および印鑑登録証明書(発行後3か月以内のもの))
です。
念のため、遺言者が亡くなる前は、遺言検索の申出は遺言者本人に限られています。
詳細は、最寄りの公証役場にお尋ねいただくことが最も手っ取り早いです。
日本公証人連合会 公証役場一覧
https://www.koshonin.gr.jp/list
3 自筆証書遺言がどこにあるか調べる方法
⑴ 法務局
令和2年7月10日以降に自筆証書遺言を作成し、法務局の遺言書保管所に遺言書を預けている場合は、遺言者死亡後において、法務局にて、遺言書情報証明書 (遺言者の氏名、出生の年月日、住所及び本籍(又は国籍等)に加え、目録を含む遺言書の画像情報が表示されるものであり、遺言書の内容の証明書となるもの)の交付請求、あるいは、遺言書の閲覧請求ができます。
後者の閲覧請求は、モニターにより遺言書の画像を見る方法と原本を直接見る方法があり、モニター閲覧であれば全国どの法務局でも行うことができます。
原本閲覧は保管した法務局のみでの閲覧となります。
閲覧方法は、以下の所定の閲覧申出書に必要事項を記載する方法で行います(最寄りの法務局の窓口でも用紙は交付しております。)。
https://www.moj.go.jp/MINJI/04.html
あとは、閲覧予約をし、以下の所定の書類を持参して閲覧します。
- ①法定相続情報一覧図(ない場合は、遺言者の出生から死亡までのすべての戸籍(除籍)謄本、相続人全員の戸籍謄本、相続人全員の住民票の写し)
- ②顔写真付きの身分証
- ③手数料(モニター閲覧1400円、原本閲覧1700円)
その他請求者が相続人以外の場合は別途必要資料があるため、法務局の遺言書保管担当に照会してください。
⑵ 法務局以外
前記以外の場合は、自宅の仏間、タンス、貸金庫、同居の家族が関係性の深い知人が保管している場合があり得るため、個別に確認するよりほかありません。
4 遺言書の有無の調査が必要な場合(遺産分割、遺留分侵害額請求)における当事務所の弁護士費用
遺言の調査が必要な場合は、おおくの事案では、遺産分割や遺留分侵害額請求が絡みます。
これらの事案を当事務所が対応する場合の費用についてご説明します。
⑴ 遺産分割
旧日本弁護士連合会の基準によると、例えば、不動産が遺産に含まれる場合、対象となる相続分の時価相当額は、相当高額になり、ご依頼し辛い場合がございます。
そのため、当事務所では、旧報酬基準を若干変更し、よりご依頼をしやすい費用形態としております。
具体的には、当事務所の遺産分割問題の報酬基準の詳細はこちらです。
⑵ 遺留分侵害額請求
遺留分侵害額請求は、請求をしてみたところ相手方が十分にお金をもっていなかったというケースがあり得、また、遺産に不動産が含まれている場合等は非常に高額な請求額になる場合があります。
そのため、遺産分割同様に、当事務所ではよりご依頼をしやすい費用形態としております。
遺留分侵害額請求(請求する側)についての費用詳細は、こちらをご覧ください。
また、遺留分侵害額請求(請求された側)についての費用詳細は、こちらをご覧ください。
5 おわりに
遺言があり得る事案で遺産分割協議を先行した結果、後に遺言が見つかると大変面倒な事態となります。
被相続人のご遺志を尊重する観点からも遺言の調査は非常に重要な手続となります。
遺言が発見された場合もされなかった場合も、相続問題には弁護士の関与が有益な場合は多くあります(発見された場合も遺言執行や遺留分侵害額請求の対応等でご依頼いただくケースがございます。)。
遺言の調査や遺産相続分野の弁護士費用を含め、何か少しでもお悩みの際は、当事務所でお力になれる可能性がありますので、まずはお気軽に弁護士までご連絡いただければと思います。
お電話でのお問い合わせ
平日9時~18時で電話対応
☎︎ 03-5875-6124