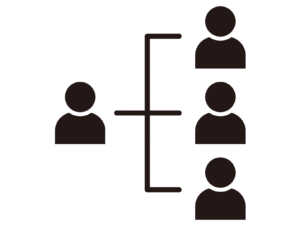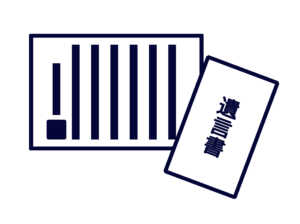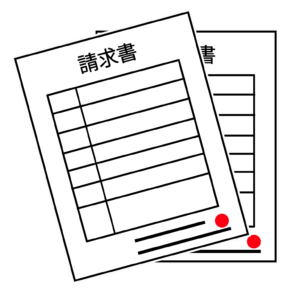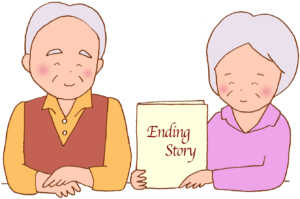「預貯金の使い込みを取り戻す」
その他
「父/母が亡くなったため、通帳(銀行取引明細)を見てみたら、亡くなる直前に多額の金額が引き出されていることが分かった。
父/母の通帳・印鑑は同居していた兄弟が管理していたので尋ねてみたところ、父/母から贈与を受けたと言って話し合いに応じない。」といった相談を受ける場合があります。
そこで、今回の記事では、預貯金の使い込みを取り戻す方法などについて解説いたします。
目次
1 預貯金の使い込みの時期
ひとくちに「預貯金の使い込み」といっても、その使い込みの時期は、大きく、①(父/母などの)被相続人が亡くなる前の使い込み、又は、②被相続人が亡くなった後の使い込みの二つに分けて考えることができます。
2 ①被相続人が亡くなる前の使い込みの場合
被相続人が亡くなる前の使い込みの場合、「被相続人は亡くなる直前に認知症になり判断能力が低下しており、銀行からの引出しを依頼したり、贈与したりする判断ができたはずはない。」などとして、無権限の引出しであることを理由に不当利得返還請求権又は不法行為による損害賠償請求権を行使していくことになります。
具体的には、被相続人の生前に被相続人の口座から二人兄弟のうち一人が1000万円を無権限で引き出していることが判明した場合には、もう一人の兄弟は、被相続人が亡くなった結果、この1000万円の不当利得返還請求権又は不法行為による損害賠償請求権の半分(法定相続分2分の1)を相続により引き継ぐことになるため、500万円の返還請求をしていくことになります。
⑴ 交渉による回収
この500万円の返還請求については、まずは内容証明郵便による請求などから始まる話し合い(交渉)によって解決の途を探ることになりますが、親族間の感情的対立や贈与の有無、引き出した金銭の使い道(葬儀費用・介護・入院費用など被相続人のための有用な使い道であったなど)といった事情から、深刻な争いに発展するケースも多くあります。
⑵ 遺産分割調停による回収
引き出した相手方が家庭裁判所における遺産分割調停において遺産として取り扱うことに同意すれば、使い込みがなされた預貯金以外の遺産と一緒に遺産分割調停の中で解決することも可能となります。
⑶ 訴訟による回収
このような遺産分割調停内での同意が得られないケースも間々ありますので、このような場合には、地方裁判所において民事訴訟を提起して解決するしかないことになります。
⑷ 主張立証の糸口
そして、民事訴訟においては裁判官を説得し返還請求認容判決を獲得するためには、話し合い(交渉)において相手方を説得する以上に、何よりも請求を支える証拠を早期に適切に揃えて、緻密な主張立証を組み立てることが重要となります。
具体的には、先に挙げた「被相続人は亡くなる直前に認知症になり判断能力が低下しており、銀行からの引出しを依頼したり、贈与したりする判断ができたはずはない。」といった主張立証を効果的に行うためには、
- ① 被相続人の預貯金通帳・印鑑の管理に関する証拠
- ② 介護記録・医療機関の診療記録などの被相続人の判断能力に関する証拠
- ③ 銀行取引明細書・払戻請求書・委任状などの引出しに関する証拠
- ④ 領収書などの引き出した金銭の使途に関する証拠
を適切に収集分析し、内容証明郵便あるいは訴状などを作成していくことが必要となります。
3 ②被相続人が亡くなった後の使い込みの場合
被相続人が亡くなった後の預貯金は、共同相続人が(準)共有していることになります。
したがって、原則としては、例えば、被相続人の死後に被相続人の口座から二人兄弟のうち一人が1000万円を引き出していることが判明した場合、もう一人の兄弟は、相続分を侵害されていることを理由として、この1000万円の半分(法定相続分2分の1)を不当利得返還請求権又は不法行為による損害賠償請求権に基づき返還請求していくことになります。
⑴ 交渉による回収
被相続人が亡くなる前の使い込み同様の手法で、まずは交渉による回収を検討してみることが考えられます。
⑵ 遺産分割調停・審判、訴訟による回収
被相続人が亡くなった後の使い込みであれば、遺産分割調停のなかで解決できないのか?と思われる方も多いかもしれませんが、遺産とは「死亡時に存在し、現在も存在する、プラスの財産」であるため、口座から引き出されて現金化してしまった等の事情により、現在は存在しない預貯金債権については、「現在も存在する」という要件を欠くので遺産とは取り扱われないことになります。
そのため、遺産分割調停で取り扱うためには、相続人全員の同意が必要になります。
引き出した者が家庭裁判所における遺産分割調停・審判の中で解決することに同意しない場合、原則として、地方裁判所で民事訴訟を提起して解決するほかありません(ありませんでした)。
⑶ 法改正に伴うもう一つの解決手段
ここまで述べた解決手段は、現在もなお、有効な解決手段です。
しかし、2018年(平成30年)に民法(相続法)が改正され、2019年(令和元年)7月1日以後に亡くなったケースでは、預貯金を引き出した者以外の相続人全員の同意があれば、死後に引き出された預貯金を遺産に組み戻し、預貯金以外のほかの遺産と一緒に家庭裁判所における遺産分割調停・審判において手続することができるようになりました。
今後は、こちらの方法に基づき、解決を目指すのが主流になっていくと思われます。
民法第九百六条の二 遺産の分割前に遺産に属する財産が処分された場合であっても、共同相続人は、その全員の同意により、当該処分された財産が遺産の分割時に遺産として存在するものとみなすことができる。
2 前項の規定にかかわらず、共同相続人の一人又は数人により同項の財産が処分されたときは、当該共同相続人については、同項の同意を得ることを要しない。
4 預貯金の使い込みに関する問題を弁護士に依頼する流れ・ご依頼後の流れ
まずは、お電話にてお気軽にお問い合わせください。
弁護士が概要をお伺いさせていただきます。
お電話で概要をお伺いした結果、事務所にお越しいただいて正式なご相談をしていただくことになった際は、日程の調整をお電話でいたします。
正式なご相談では、手続の流れ、所要時間、弁護方針、費用のお見積りを三色ペンで図示しながら行います。
相談料は、初回30分は無料となります。
相談の結果、ご依頼を決めた場合は、契約書を取り交わして、弁護活動をスタートします。
5 預貯金の使い込みに関する問題の弁護士費用
弁護士費用は事務所によってまちまちです。
ここでは当事務所の弁護士費用について説明をします。
弁護士費用は、法律相談料、着手金、報酬金、実費等に大きく分けられます。
上記についての詳細は、こちらをご覧ください。
預貯金の使い込みに関する費用については、こちらをご覧ください。
6 おわりに
以上解説いたしましたとおり、被相続人の生前・死後の預貯金の使い込みを取り戻すためには、①いかなる証拠に基づき効果的な主張立証を組み立てるべきか、②請求(回収)のためにどのような解決手段(交渉、遺産分割調停・審判、民事訴訟等)を取るべきかなど、考えなければならないポイントが数多くあります。
このような問題に直面された場合には、法的な専門知識が必要となりますので、まずはお気軽に弁護士にご相談いただければと思います。
お電話でのお問い合わせ
平日9時~18時で電話対応
☎︎ 03-5875-6124