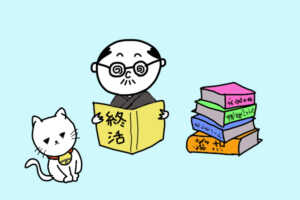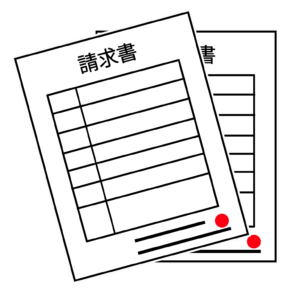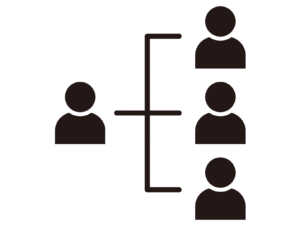夫(妻)の死後、今の家に住み続けられる?「配偶者短期居住権」をわかりやすく解説
その他
大切なご家族を亡くされ、深い悲しみの中にいらっしゃる中で、今後の生活、特に「住まい」について大きな不安を抱えていらっしゃる方は少なくありません。
「夫が亡くなった後、このまま家に住み続けられるだろうか」
「他の相続人から『家を売って遺産を分けたいから出て行ってほしい』と言われたらどうしよう」
といったご相談は、私ども弁護士にも多く寄せられます。
2020年4月1日に施行された改正相続法により、そのような不安を抱える残された配偶者の居住権を保護するための新しい制度が創設されました。
その一つが、今回解説する「配偶者短期居住権」(民法第1037条)です。
この記事では、遺産分割が終わるまでの間、あるいは少なくとも相続開始から6か月間、配偶者が安心してご自宅に住み続けることができる「配偶者(短期)居住権」について、その仕組みや注意点を弁護士がわかりやすく解説します。
参照 条文
(配偶者短期居住権)
第1037条
① 配偶者は、被相続人の財産に属した建物に相続開始の時に無償で居住していた場合には、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める日までの間、その居住していた建物(以下この節において「居住建物」という。)の所有権を相続又は遺贈により取得した者(以下この節において「居住建物取得者」という。)に対し、居住建物について無償で使用する権利(居住建物の一部のみを無償で使用していた場合にあっては、その部分について無償で使用する権利。以下この節において「配偶者短期居住権」という。)を有する。ただし、配偶者が、相続開始の時において居住建物に係る配偶者居住権を取得したとき、又は第891条の規定に該当し若しくは廃除によってその相続権を失ったときは、この限りでない。
一 居住建物について配偶者を含む共同相続人間で遺産の分割をすべき場合 遺産の分割により居住建物の帰属が確定した日又は相続開始の時から六箇月を経過する日のいずれか遅い日
二 前号に掲げる場合以外の場合 第三項の申入れの日から六箇月を経過する日
② 前項本文の場合においては、居住建物取得者は、第三者に対する居住建物の譲渡その他の方法により配偶者の居住建物の使用を妨げてはならない。
③ 居住建物取得者は、第一項第一号に掲げる場合を除くほか、いつでも配偶者短期居住権の消滅の申入れをすることができる。
目次
1. 配偶者短期居住権とは?~残された配偶者の生活を守る権利~
配偶者短期居住権とは、一言でいえば、「被相続人(亡くなった方)が所有する建物に無償で住んでいた配偶者が、相続開始後、一定期間そのまま無償で住み続けることができる権利」です。
この権利は、遺産分割協議や遺言、家庭裁判所の審判などがなくても、法律で定められた要件を満たせば当然に発生します。これにより、残された配偶者は、相続手続が進んでいる間、急に住む場所を失うという事態を避けることができるようになりました。
例えば、夫が亡くなり、自宅は夫名義。相続人が妻と、夫と疎遠だった兄弟だったとします。もし夫の兄弟が「法律上の権利があるのだから、すぐに家を売却して現金で分けたい」と主張してきたとしても、妻はこの配偶者短期居住権を根拠に、すぐに退去する必要はなく、一定期間は住み慣れた家での生活を継続できるのです。
これは、長期的な居住を保障する「配偶者居住権」とは異なり、いわば遺産分割などが落ち着くまでの「応急処置」的な権利とイメージしていただくと分かりやすいかもしれません。
2. 配偶者短期居住権が成立するための2つの要件
配偶者短期居住権は、以下の2つの要件を満たすことで自動的に成立します。
要件1:法律上の配偶者であること
この権利が認められるのは、被相続人の法律上の配偶者に限られます。したがって、長年連れ添った事実婚(内縁)のパートナーや、同性のパートナーには、残念ながら配偶者短期居住権は認められません。もっとも、今回は割愛しますが、黙示の使用貸借契約により居住する余地はありますので、このようなケースで居住を希望する場合は特に弁護士にご相談ください。
要件2:相続開始時に、被相続人の遺産である建物に無償で住んでいたこと
配偶者が、相続が開始した時点(=被相続人が亡くなった時点)で、対象となる建物に生活の本拠として無償で居住している必要があります。
ここで重要なのは「無償で」という点です。もし配偶者が被相続人に対して家賃を支払って建物を借りていた場合、それは「賃貸借契約」となり、配偶者短期居住権は発生しません(その代わり、賃借人としての権利が保護されます)。
【Q&A】よくあるご質問
Q. 夫とは同居していませんでしたが、夫名義の家に住んでいました。この場合も対象になりますか?
A. はい、対象になります。被相続人との同居は要件ではありません。配偶者が生活の本拠としてその建物に居住していれば問題ありません。
Q. 夫は亡くなる前、介護施設に入居していました。私も一緒に施設に移っていましたが、自宅は夫名義のままです。この場合はどうなりますか?
A. ご夫婦が共に施設に入居していた場合でも、その家が生活の本拠であったと認められれば、配偶者短期居住権は成立する可能性があります。個別の事情によりますので、弁護士にご相談ください。
3. いつまで住み続けられる?~配偶者短期居住権の期間~
配偶者短期居住権で保護される期間は、「誰がその建物を相続(又は遺贈)したか」によって、2つのパターンに分かれます。ここが少し複雑な部分ですので、ご自身の状況と照らし合わせてご確認ください。
パターン1:自宅が「遺産分割の対象」となる場合
配偶者を含む共同相続人の間で、誰がその家を相続するのかを話し合う(遺産分割協議を行う)ケースです。
この場合、住み続けられる期間は、以下のいずれか遅い日までとなります。
遺産分割によって家の所有者が確定した日
相続開始の時(亡くなった日)から6か月が経過する日
【具体例】
2025年4月1日に夫が亡くなった事例。この事例の場合、最低でも、6か月後の2025年10月1日までは居住が保証されます。
もし遺産分割協議が長引き、家の相続人が決まったのが2026年3月1日だった場合
→ この「遅い日」である2026年3月1日まで住み続けることができます。
つまり、遺産分割協議が続いている間は、少なくとも相続開始から6か月間は居住権が保護され、協議が6か月を超えて長引けば、その協議がまとまるまで住み続けることができる、ということになります。
パターン2:自宅が「遺産分割の対象外」となる場合
遺言によって配偶者以外の第三者(例えば、愛人や知人、お世話になった団体など)に遺贈された場合や、「特定の相続人(配偶者以外の子など)に相続させる」旨の遺言があった場合、また、配偶者自身が相続放棄をした場合などがこのパターンに該当します。
この場合、住み続けられる期間は、家の新しい所有者から「配偶者短期居住権を消滅させる」という意思表示(消滅の申入れ)をされた日から、6か月が経過する日までとなります。
【具体例】
遺言により、夫の愛人が自宅を譲り受けることになった事例で、愛人(新しい所有者)から、妻に対して「出ていってほしい(短期居住権の消滅を申し入れる)」という通知が2025年5月1日に届いた。
→ その日から6か月後の2025年11月1日まで妻は住み続けることができます。
【注意点】
このパターン2の場合、新しい所有者から消滅の申入れがなければ理論上は住み続けることも可能ですが、いつ申入れをされるか分からない、非常に不安定な立場に置かれることになります。遺言でご自宅が第三者に渡ることが判明した場合は、速やかに弁護士に相談し、今後の対応を検討することをお勧めします。
4. 配偶者短期居住権の注意点~知っておくべき義務と制限~
配偶者短期居住権は、配偶者の居住を保護する強力な権利ですが、無制限に何でもできるわけではありません。知っておくべき義務と制限があります。
⑴ 守るべき義務
ア 善良な管理者の注意をもって使用する義務(善管注意義務)
他人の物を借りているのと同じように、社会通念上要求される程度の注意を払って、建物を維持・管理する義務があります。故意に建物を壊したり、適切な管理を怠って損傷させたりした場合は、損害賠償を請求される可能性があります。
イ 建物の通常の必要費を負担する義務
建物の使用に伴って通常発生する費用(小規模な修繕費など)は、居住している配偶者が負担します。なお、固定資産税については、原則としてその年の1月1日時点の所有者(又は相続人)に納税義務がありますが、遺産分割協議の中で配偶者が負担するよう取決めがなされることもあります。
⑵ できないこと(制限)
ア 建物の増改築
建物の所有者の承諾がなければ、増改築を行うことはできません。
イ 第三者への賃貸(収益化)
この権利はあくまで配偶者自身の居住を保護するためのものです。したがって、建物を第三者に貸して家賃収入を得ることは認められていません。
ウ 権利の譲渡
配偶者短期居住権を他人に譲渡することはできません。
⑶ 権利が消滅する場合
以下の事由に該当した場合、配偶者短期居住権は消滅します。
・上記の存続期間が満了したとき
・配偶者が死亡したとき
・建物が火災などで全部滅失したとき
・配偶者が配偶者(長期)居住権を取得したとき
・用法違反などにより、建物の所有者から消滅請求をされたとき
5. 「配偶者居住権」との違いは?
相続法改正では、「配偶者短期居住権」とともによく似た名前の「配偶者居住権」という権利も創設されました。この2つは目的や性質が大きく異なるため、混同しないように注意が必要です。
簡単に言えば、「短期居住権」が遺産分割などが終わるまでの短期的な居住を確保する“つなぎ”の権利であるのに対し、「居住権」は配偶者が生涯(又は一定期間)、長期的に住み続けることを保障する権利です。
配偶者居住権を取得すれば、たとえ家の所有権が他の相続人(例えば子)に移ったとしても、配偶者は亡くなるまで安心して住み続けることができます。どちらの権利がご自身の状況に適しているか、また配偶者居住権の取得を目指すべきかについては、遺産総額や他の相続人との関係などを踏まえた専門的な判断が必要です。
6. 配偶者短期居住権と相続税
相続問題を考える上で、税金の問題は避けて通れません。配偶者短期居住権と相続税の関係について、重要なポイントを2つ押さえておきましょう。
⑴ 配偶者短期居住権そのものに相続税はかからない
配偶者短期居住権は、相続税の課税対象となる財産には含まれません。したがって、この権利が発生しても、配偶者の相続税額が上がることはありません。
⑵ 短期居住権があっても、建物の相続税評価額は下がらない
遺言などにより、配偶者以外の第三者が建物を取得した場合を考えてみましょう。取得者から見れば、配偶者が最低6か月は住み続けるため、その間は建物を自由に使えないという「負担」が付いていることになります。しかし、相続税の計算上、この負担を理由に建物の評価額を減額することは認められていません。取得者は、負担が付いたままの状態で評価された建物の相続税を納める必要があります。
税金の詳細な計算や申告は税理士の専門分野となりますが、私ども弁護士は、税理士と連携しながら、相続手続き全体を見据えた最適な解決策をご提案することが可能です。
7. こんな時は弁護士にご相談ください
配偶者短期居住権は自動的に発生する権利ですが、その期間の計算が複雑であったり、他の相続人との交渉が必要になったりと、当事者だけでの解決が難しいケースも少なくありません。もし、以下のような状況でお悩みでしたら、お一人で抱え込まず、お早めに弁護士にご相談ください。
他の相続人から、すぐに家から出ていくよう要求されて困っている。
遺言書が見つかり、自宅が自分以外の第三者に遺贈されていることがわかった。
遺産分割協議がまとまらず、この先いつまで今の家に住めるのか不安だ。
短期的な居住だけでなく、今後も長く住み続けるために「配偶者居住権」の取得を検討したい。
相続財産がどのくらいあるのか、相続人が誰なのかもはっきりせず、何から手をつけていいかわからない。
8.まとめ
配偶者短期居住権は、残された配偶者が相続という混乱期において、ひとまず住み慣れた家での生活を続けられるように保障する、非常に重要な権利です。
ご自身にこの権利があることを知っているだけでも、精神的な安心につながり、他の相続人との話合いにも落ち着いて臨むことができるでしょう。
しかし、その内容は決して単純ではなく、個々の事情によっていつまで住めるのか、どのような義務を負うのかが変わってきます。相続を「争続」にしないためにも、そしてご自身の正当な権利を守るためにも、少しでもご不安な点があれば、相続問題に詳しい専門家である弁護士にご相談いただくことを強くお勧めします。
当事務所では、相続に関する様々なお悩みに対応しております。初回のご相談は無料ですので、どうぞお気軽にお問い合わせください。
お電話でのお問い合わせ
平日9時~18時で弁護士が電話対応
※初回ご来所相談30分無料
☎︎ 03-5875-6124