遺留分侵害額の計算方法と弁護士に依頼した場合の費用とメリット
その他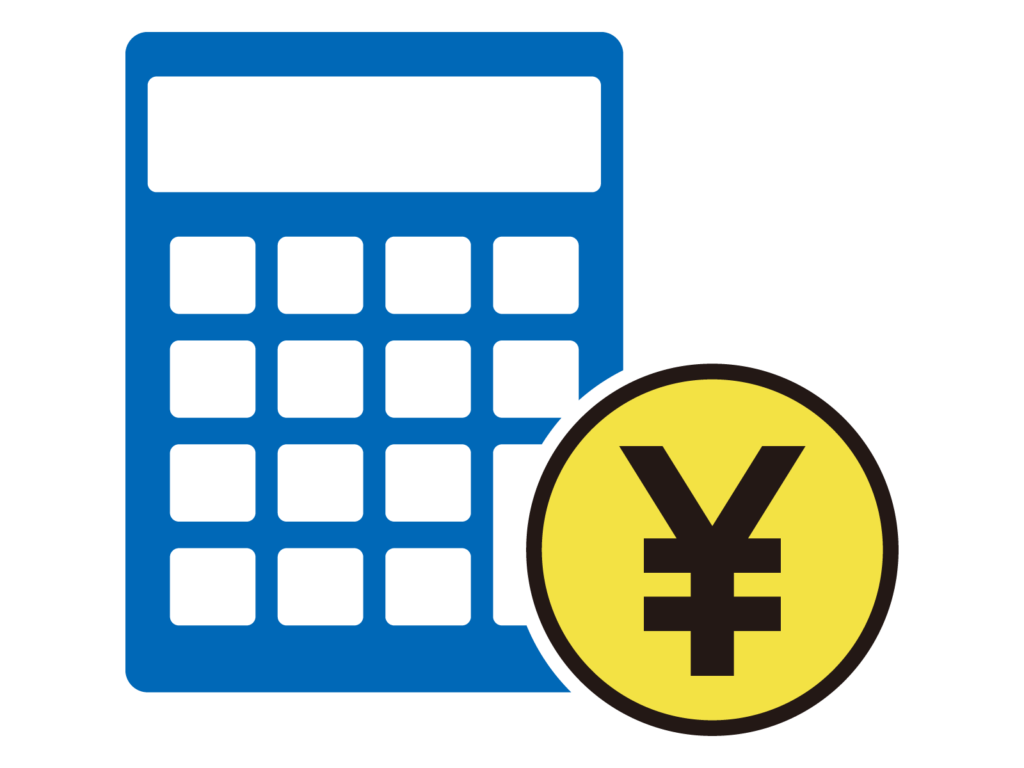
「兄弟にすべての財産を相続させる内容の不平等な遺言書が見つかりました。他の相続人に遺留分を主張したいのですが、どのような手続をとればいいのでしょうか。」
「遺産相続における遺留分の計算はどのようにすればよいのでしょうか。」
このようなご質問は、多くのお客様から寄せられるご質問です。
このコラムでは、相続問題のうち遺留分に関する計算方法や遺留分侵害額請求についての具体例を用いた実際の計算について説明をします。
目次
1 遺留分とは
遺留分とは、一定の相続人について、被相続人(亡くなった方)の財産から法律上取得することが保障されている最低限の取り分のことです(民法第1042条参照)。
この取り分は、被相続人の生前の贈与や遺贈によっても奪われることはありません。
被相続人は、相続の場面において、生前贈与や公正証書遺言・自筆証書遺言等を利用して、自分の財産を自由に処分できるのが原則です。
しかし、その結果、本来であれば遺産を相続できたはずの相続人が、遺産を相続できないということが起こり得ます。
そこで、一定の相続人の生活保障の観点から設けられたのが遺留分制度です(民法第1046条 遺留分侵害額の請求 ※かつては、遺留分減殺請求という制度でしたが、法改正により遺留分侵害額請求となりました。
名称だけではなく内容にも若干違いはありますが、本稿においては詳細を割愛いたします。)。
2 遺留分の権利を有する相続人の範囲
⑴ 遺留分の権利
遺留分の権利(遺留分権)を有する相続人(遺留分権利者)は以下のとおりです。
全ての相続人が遺留分権を有する訳ではありません。
① 配偶者
夫や妻が相続人になる場合、遺留分が認められます。
② 子供や孫などの直系卑属
子供や孫、ひ孫などの被相続人の直接の子孫を「直系卑属」といい、遺留分が認められます。
③ 親や祖父母などの直系尊属
親や祖父母、曾祖父母などの被相続人の直接の先祖のことを「直系尊属」といい、遺留分が認められます。
⑵ 被相続人
他方、被相続人の兄弟姉妹や、兄弟姉妹が先に亡くなっている場合に相続人となる甥や姪には遺留分は認められません。
3 遺留分の計算方法
⑴ 総体的遺留分と個別的遺留分
遺留分の割合を計算するに当たっては、まず、全体としてどのくらいの遺留分が認められるのかという「総体的遺留分」を計算し、続いて、個別の遺留分権利者の遺留分割合である「個別的遺留分」を計算します。
⑵ 総体的遺留分率
総体的遺留分率は、誰が相続人になるかによって異なります。
親や祖父母などの直系尊属のみが相続人の場合
被相続人の親や祖父母などの直系尊属のみが相続人の場合、総体的遺留分率は遺産全体の3分の1です。
それ以外の場合
被相続人の配偶者や子供が相続人の場合や被相続人の配偶者と被相続人の親が相続人の場合、総体的遺留分率は、遺産全体の2分の1です。
⑶ 個別的遺留分率
各相続人の個別的遺留分率は、総体的遺留分に各相続人の法定相続分割合を掛けて算出します。
具体的には、被相続人の妻と子供2人(長男、次男)が相続人の場合、総体的遺留分率は2分の1ですので、それに妻の法定相続分2分の1、長男の法定相続分4分の1、次男の法定相続分4分の1を子供のそれぞれ掛けるので、各相続人の個別的遺留分率は、
長男が8分の1
次男が8分の1
となります。
⑷ 遺留分の基礎となる財産
遺留分の算定の基礎となる財産は、
① 被相続人の死亡時の財産に、
② 被相続人が贈与した財産(被相続人の死亡前1年間にされた贈与、被相続人の死亡前10年間にされた相続人に対する生前贈与など)を加え、
③ 被相続人の負債を引いたものとなります。
【具定例】
被相続人が妻に全ての財産を相続させる旨の遺言を作成していた事案において、被相続人の死亡時の預貯金(=財産)が6000万円、債務(=負債)が3000万円(負債については特に取決めがないため、相続人が法定相続分でそれぞれ承継)。
相続人は妻、長男、長女の3人であるところ、長男に対して1000万円の生前贈与がされていたというケースを想定します。
この場合、遺留分の算定の基礎となる財産は、
となります。
そして、本事案の場合、各相続人の個別的遺留分額(最低額確保できる額)は、
長男が4000万円 × 1/2 × 1/4 = 500万円
長女が4000万円 × 1/2 × 1/4 = 500万円
となります。
4 遺留分侵害額請求
被相続人が財産を遺留分権利者以外に贈与又は遺贈し、遺留分に相当する財産を受け取ることができなかった場合、遺留分権利者は、贈与又は遺贈を受けた者に対し、遺留分を侵害されたとして、その侵害額に相当する金銭の支払を請求することできます。
これを「遺留分侵害額の請求」といいます。
先ほど3の⑷で想定した事例で見ますと、実際に、妻に対し、長男と長女が請求できる遺留分侵害額を計算するためには、もう一段回計算が必要となります。
実際に現在分配されている額を計算しなければなりません。
となります。
遺留分侵害額の計算は、個別的遺留分額 - 遺留分を請求しようと思っている方の現在分配額で算出することになります。
先ほどのケースを前提とすると、
長女の個別的遺留分額500万円 - 長女の現在分配額-750万円 = 長女の遺留分侵害額1250万円
となります。
そのため、長男は妻に対し250万円を、長女は妻に対し1250万円を遺留分侵害額として請求できる計算となります。
なお、遺留分侵害額の請求は、遺留分に関する権利を行使する旨の意思表示を相手方にする必要がありますが、家庭裁判所の調停を申し立てただけでは相手方に対する意思表示とはなりませんので、調停の申立てとは別に内容証明郵便等により意思表示を行う必要があります。
この遺留分に関する権利を行使する旨の意思表示をしないときは、遺留分侵害額請求権は、相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から1年を経過したときに時効によって消滅します。
また、相続開始の時から10年を経過したときも同様です。
5 当事務所の遺留分侵害額請求に関する弁護士費用
当事務所の遺留分侵害額請求(請求する側、される側)の費用は次のページをご参照ください。
6 遺留分に関する手続を弁護士に依頼するメリット
遺留分侵害があるかどうかを判断するに当たっては、相続財産の調査や、これを前提とした複雑な計算が必要となりますし、遺留分侵害額請求の手続も、その手順を誤ると時効によって請求することができなくなるなど、専門知識が必要です。
加えて、実務上、前述のケースのようなキリの良い数値であることはあり得ないため、極めて細かい数値になり、その複雑な計算も相まって、誤算を招く危険も高い事案といえます。
たとえば遺言書の記載から相続財産が漏れており、遺留分の問題以外に遺産分割(遺産相続)の手続を別途行わなければならないケースや、その遺産分割の結果を遺留分侵害額請求の際に考慮しなければならない場合もままあります。
さらにいえば、遺留分は遺留分額が確定した日の翌日から4カ月以内に修正申告や期限後申告を行わなければ延滞税や加算税の支払い義務を負う場合があります。
当事務所の代表弁護士は税理士資格も保有しており、地域の相続税専門の税理士とも連携が可能ですので、税理士のご紹介を希望される際は、ご遠慮なくご相談ください。
東京、千葉、埼玉、茨城など関東近郊で遺留分に関するトラブルでお悩みの際は、まずは財産調査や試算からも承っておりますので、お気軽にご相談ください。
お電話でのお問い合わせ
平日9時~18時で電話対応
☎︎ 03-5875-6124










